介護職が知っておきたい:天気や気候が高齢者の心身に与える影響と利用者様・私たち自身のケア
少し肌寒さを感じる朝は、私自身の体も心も、なんとなく重く感じたり、シャキッとしにくいな…と思うことがあります。これは多くの人が経験することですが、介護職である私たち自身のコンディションも、日々のケアに影響します。
今日も、そんなひんやりとした空気の中、いつもの訪問先へ向かいました。
ドアを開けて迎えてくださった利用者様の表情は、どこか曇りがちで、眉間にはうっすらしわが寄っています。体調が特に悪いというわけではなさそうでしたが、窓の外の天気を気にする様子が何度もうかがえました。
「あなたは若いから、元気でいいねぇ」と仰る声も、普段より少し元気がないように感じます。会話の途中には何度かため息も聞こえてきて、「今日外はどう?寒いでしょ?少し寒いからか腰が痛いし、体もスッキリしないのよ。嫌になっちゃう」「楽しい事が考えられなくてどんどん暗くなっちゃう」と、正直な気持ちをお話ししてくださいました。
【介護の視点】気候変動(気圧・気温・湿度など)が高齢者の心身に与える影響を理解する
介護の現場で利用者様が天候によって体調や気分を崩される様子は珍しくありません。特に高齢者の方は、気圧の変化や寒暖差、湿度の影響を受けやすく、様々な不調として現れることがあります。
体への影響:
-
気圧の変化: 低気圧が近づくと、自律神経のバランスが乱れやすくなり、頭痛、めまい、だるさ、関節や古傷の痛みが増強することがあります。「天気痛(気象病)」とも呼ばれ、高齢者の場合は体の調節機能が低下しているため、より強く症状を感じる場合があります。
-
気温や湿度: 寒さは体の血行不良を引き起こし、筋肉のこわばりや関節痛の悪化につながります。また、乾燥は皮膚トラブルを招きやすく、湿度が高いとむくみやだるさを感じやすくなります。
心への影響:
-
日照時間: 日照時間が短くなる季節(特に冬場)は、精神の安定に関わるセロトニンなどの分泌が減少しやすく、気分の落ち込み、意欲の低下、不眠といった「季節性うつ」のような症状が見られることがあります。
-
体調不良からの影響: 体の不調が続くと、「嫌になっちゃう」「楽しいことが考えられない」といったネガティブな感情や、不安、苛立ちにつながりやすくなります。
利用者様の「腰が痛いし、体もスッキリしない」「楽しい事が考えられなくてどんどん暗くなっちゃう」といった言葉は、まさに気候が心身両面に影響を与えているサインと捉えることができます。
利用者様の訴えに寄り添う傾聴と、その方らしさを引き出す関わり
このような訴えがあった際には、まずはその方のつらい気持ちを傾聴し、共感の姿勢を示すことが何より大切です。「お天気のせいもあるかもしれませんね」「体がだるいと何もかも嫌になりますよね」といった言葉で、感情を受け止めていることを伝えましょう。安易に「大丈夫ですよ」「気にしないで」と励ますよりも、まずは「つらいですね」と一緒に感じている姿勢を見せることが、利用者様の安心に繋がります。
しかし、そんな体調や気分の波がある中でも、利用者様は「次は〇〇してもらおうかな」といつものように仕事の指示をくださったり、しっかりされている様子も見せてくださいました。この「いつものその方らしさ」が垣間見える瞬間に気づくことは、私たち介護職にとって大切な観察力です。これは、体調や気分に左右されながらも、その方の持つ力や、役割を果たそうとする気持ちが失われていないことを示しています。
具体的な関わりのヒント:
-
体調への配慮: 寒い日であれば、室内温度の調整、温かい飲み物の提供、ひざ掛けの利用などを促し、物理的な快適さを提供する。
-
無理のない気分転換: 体調が優れない時に無理に活動を促すのは逆効果です。まずはゆったり過ごしていただきながら、好きな音楽をBGMで流す、昔の楽しかった出来事の写真を一緒に見る、短い時間でも窓の外の景色を眺めるなど、心身への負担が少ない気分転換を提案してみる。
-
非言語コミュニケーションとユーモアの活用: 言葉だけでなく、優しい笑顔、穏やかな表情、適度な声のトーン、そして利用者様との関係性やその方の性格によっては、場を和ませるための少しオーバーなジェスチャーやユーモアも非常に有効です。今回私が思わずしてしまった「踊ってみせた」という行動のように、予期せぬ、遊び心のある行動は、張り詰めた場の空気を変え、利用者様の感情にポジティブな変化をもたらすことがあります。もちろん、これは状況や利用者様をよく見て判断することが大切です。
-
「できたこと」に焦点を当てる: 体調が優れない日でも、「お茶を自分で淹れられましたね」「少しお話できましたね」など、その日できたことや、その方の良い点に焦点を当てて声かけすることで、自己肯定感を高めるサポートができます。
介護職自身のセルフケアの重要性
繰り返しになりますが、私たち介護職自身も、気候や日々のケアによる心身の負荷の影響を受けます。利用者様に最善のケアを提供するためにも、私たち自身の体調やメンタルヘルスを良好に保つことが不可欠です。
なんとなく体や気分が重い朝は、「今日はこんな感じだな」と自分の状態を認識し、無理しすぎないように意識するだけでも違います。短い休憩時間にストレッチをする、温かい飲み物で体を温める、信頼できる同僚と少し話すなど、自分なりのリフレッシュ方法を持つことが重要です。あなたが元気でいることが、利用者様への安心感にもつながります。
日々の関わりが誰かの光になる
完璧な言葉やマニュアル通りの対応だけが、介護の仕事ではありません。体調や気分の波がある利用者様に、ただ「そこにいる」というあなたの存在自体が、そして、今日のような少しの配慮や、温かい言葉かけ、そして思わず出たユーモアといった「ふとした関わり」が、利用者様にとってどれだけ大きな心の支えになっているか。今日の利用者様の「ふっとした笑顔」が、そのことを改めて教えてくれました。その笑顔に、私自身が救われた気持ちになったのです。
寒い日、曇りの日、なんとなく元気が出ない日。そんな日でも「いつものあの人が来てくれる」「自分のことを気にかけてくれる人がいる」という安心感は、高齢者の方々にとってかけがえのないものです。そして、それは、介護の現場にいる私たちだからこそ提供できる、温かいケアの形だと信じています。
あなたの、そしてすべての介護職の皆様の日々の頑張りが、きっと誰かの心に優しく灯る「小さな光」になっています。
今日も一日、本当におつかれさまでした。そして、毎日利用者様と向き合うあなた自身に、「よく頑張ったね」と声をかけてあげてください。
【免責事項】
この記事は、介護の現場での経験や一般的な情報に基づいて作成されています。医学的な診断や特定の症状の治療を目的としたものではありません。
記事中に記載されている体調や症状に関する情報は、あくまで一般的な知識として参考にしてください。個別の症状や体調不良については、必ず医師や専門家にご相談ください。
記事の内容によって生じたいかなる損害についても、当ブログでは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

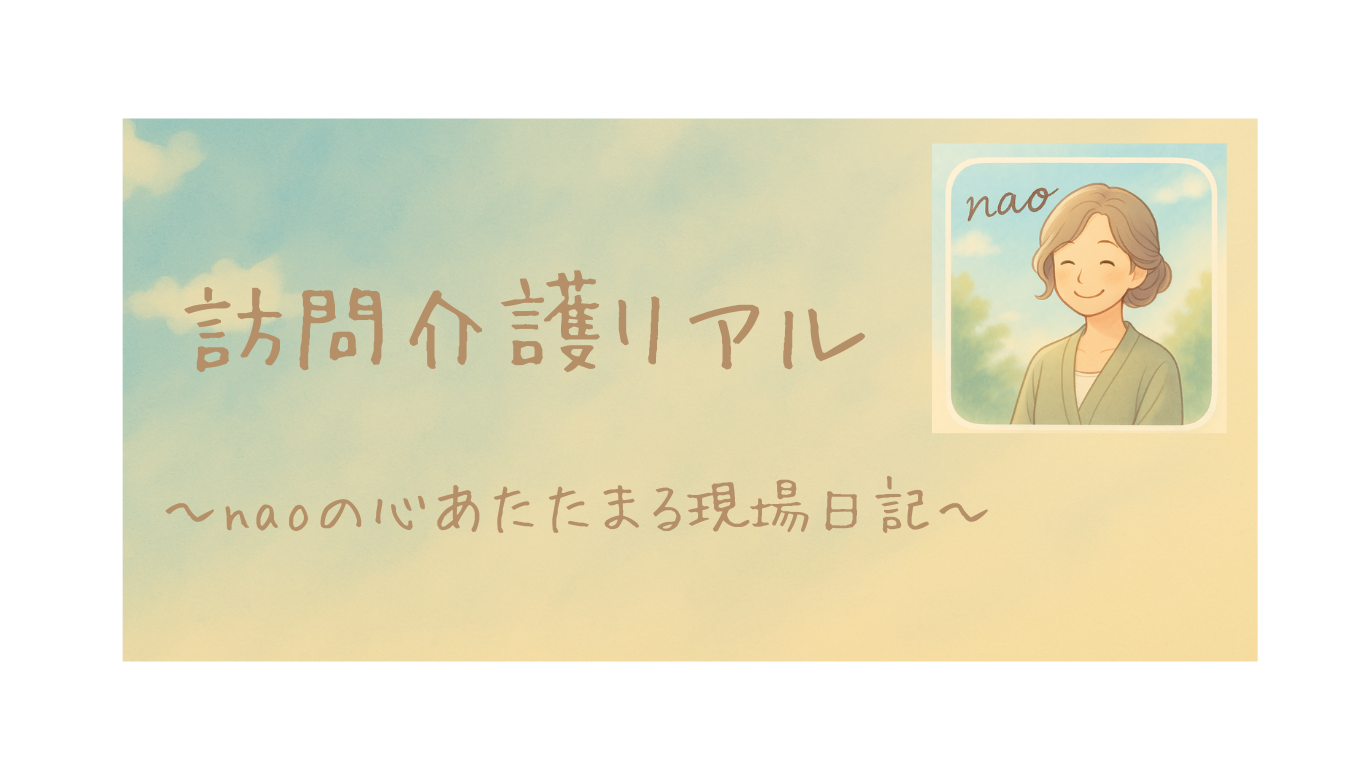



コメント